























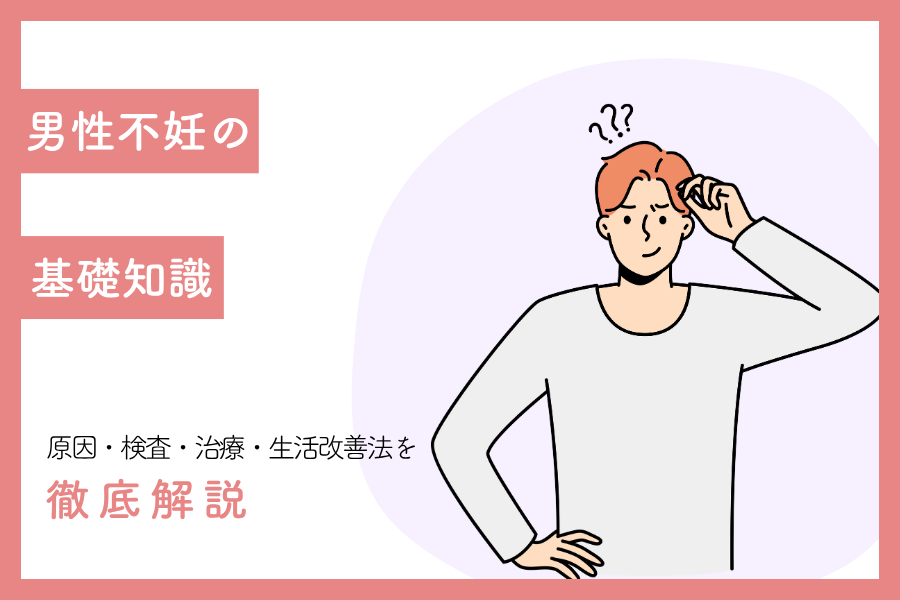
「不妊=女性側の問題」という誤解は今も根強くありますが、実際には不妊カップルの約半数に男性因子が関わっているとされています。近年は精子数の減少や精液所見の悪化が世界的に報告されており、男性不妊の理解と対策はますます重要になっています。
この記事では、男性不妊の原因・検査・治療法・そして日常生活でできる改善策について解説します。

男性不妊とは、妊娠を希望するカップルにおいて、男性側の要因によって自然妊娠が難しい状態を指します。国際的には、避妊をせずに1年間性交しても妊娠しない場合を「不妊」と定義します。そのうち男性因子が関与する割合はおよそ50%にのぼります(*1)。
さらに、195の国と地域における不妊症の頻度を調査してきたGlobal Burden of Disease Studyの報告では、1990年から2017年の男性不妊症の年齢調整有病率は1年あたり0.291%ずつ上昇しているとされており、今後も上昇していくと思われています(*2)。

男性不妊の原因は、大きく分けて3つあります(*3)。
精子を十分につくることができない状態で、男性不妊の約8割を占める最も多い原因といわれています。はっきりした理由がわからないことも多いですが、代表的な例としては「精索静脈瘤」があります。これは精巣周囲の静脈が拡張し、精子の形成に悪影響を及ぼす病気です。治療は手術による改善が一般的です。

勃起や射精がうまくいかず、性交が成立しないケースです。性に関する理解不足や誤った自慰習慣が関わる場合もあります。また、妊活中に「排卵日に合わせなければならない」という心理的なプレッシャーが、勃起障害を引き起こすことも少なくありません。治療は原因に応じて、内服薬やカウンセリングなどが行われます。
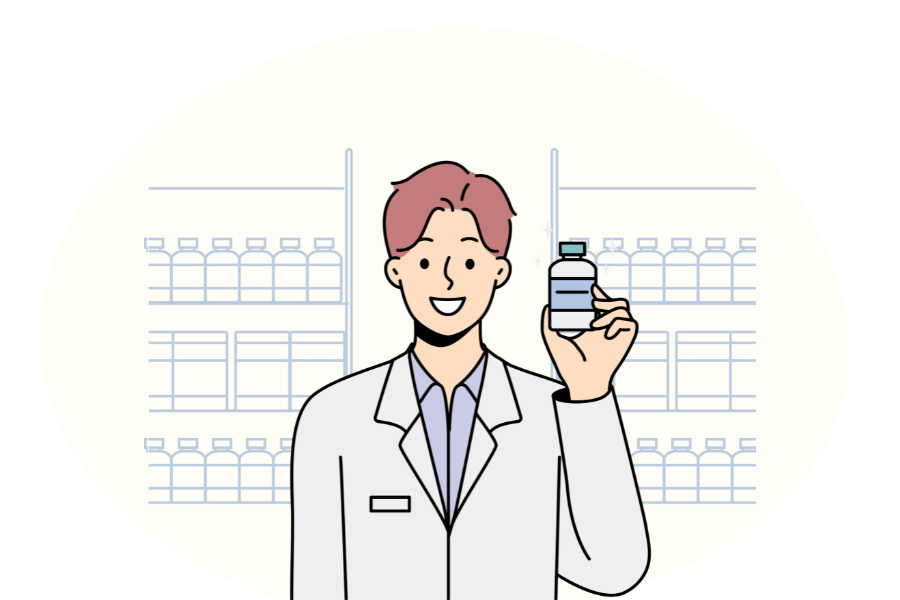
精巣で作られた精子は、精管や射精管を通って外に出ます。しかし、生まれつき精管がない場合や、炎症などで通り道がふさがってしまった場合、精子がつくられていても射出されません。精液に精子が確認できなくても、精巣内に精子が存在すれば、体外受精や顕微授精によって妊娠の可能性があります。

「造精機能障害」や「精路通過障害」が原因となり、精液中に精子が全く見られない状態を無精子症といいます。原因によって治療法は異なるため、まずは検査を受けて自分の状態を正しく知ることが、妊活の第一歩となります。

現状では、男性の妊孕性を評価する方法は「精液検査」しかありません(*1)。将来的には、精液検査以外の新しいスクリーニング法の開発も期待されています。精液検査で異常が見つかった場合は、問診・身体診察・陰嚢超音波検査・ホルモン検査・染色体検査など、より詳しい検査を受けることが必要です。
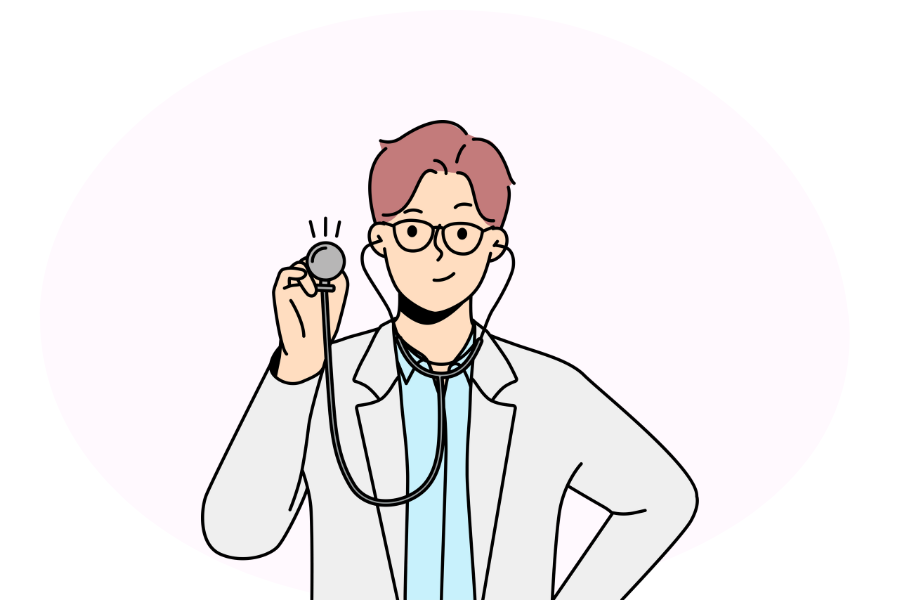
精液検査は不妊治療を専門とするクリニックで受けられ、検査前には 2〜7日間の禁欲期間 を設けます。精液はマスターベーションで採取し、自宅で持参する方法と院内で採取する方法があります。
検査では 精液量・精子濃度・精子の運動率 などを測定し、WHO基準をもとに評価されます。体調によって結果が変動するため、2回以上の検査で判断することが推奨されています。

男性不妊の治療は、精液の状態や症状の程度によって選択肢が異なります(*4)。ここでは軽度~中等度と高度(無精子症や重度精液所見不良) に分けて解説します。
喫煙、過度の飲酒、精子形成に影響する薬剤は可能な範囲で中止します。サウナや長風呂、膝上でのPC使用など、高温環境を避けることも大切です。
漢方薬、ビタミン剤、血流改善薬などを用いる方法です。統計的に有効性が確立されているわけではなく、経験的な治療が中心となります。
hCG・FSH療法やクロミフェンを用い、下垂体や精巣の働きを促すことで精子数や運動率の改善を目指します。特に低ゴナドトロピン性性腺機能低下症では、無精子症でも精液所見の改善が期待できます。
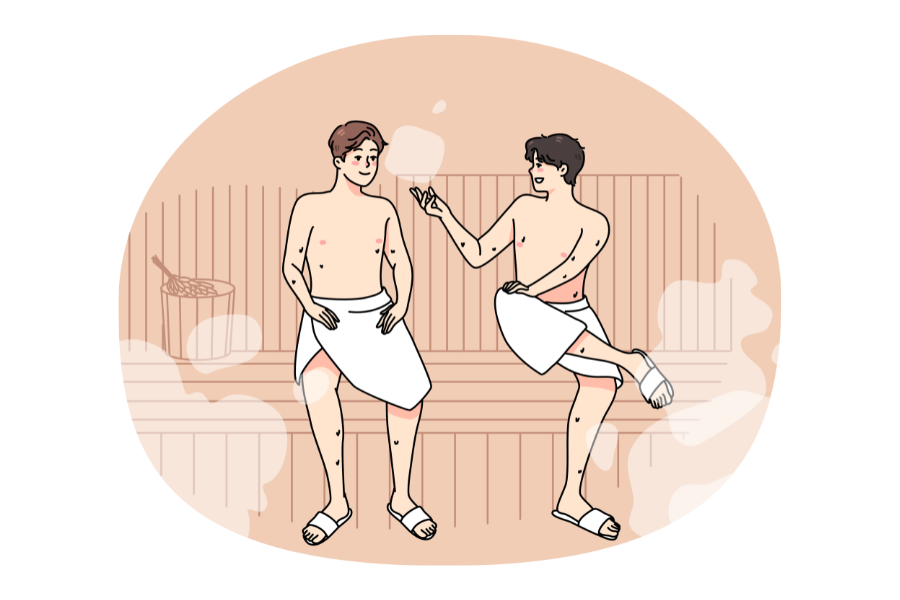
精液性状が軽度~中等度の場合、人工授精によって妊娠が確立する可能性があります。

精索静脈瘤があると精液所見の悪化や精子DNAの損傷、男性ホルモン低下の原因となることがあります。精索静脈瘤手術では、逆流する静脈を結紮(けっさつ:血管をしばって血行を止めること)します。術後の精子形成や妊娠率の改善が期待されます。

精巣組織を採取し、精子を確認できれば顕微授精に使用します。閉塞性無精子症では多くの場合採取可能です。
精巣を切開せず、精巣上体から精子を採取する方法です。
非閉塞性無精子症の場合に、精子形成がある場所を顕微鏡で探し採取します。採取できない場合もあります。

精路の閉塞を解消し、射出精液中に精子を戻すことで自然妊娠の可能性を高めます。術後の精子出現率は閉塞部位や原因により異なります。
精巣精子採取術でも精子が得られない場合や、高度精液不良で妊娠に至らない場合、夫以外の提供者の精子を用いた人工授精が検討されることもあります。
ただし、妊娠率は高いとは言えないのが現状であること、そして父子の遺伝的関係がないことや将来子どもに伝えるかなど様々な問題もあり、慎重な検討が必要です。

男性不妊は生活習慣病と関連があるとされ、高血圧・心血管疾患・脂質異常症・高尿酸血症などの疾患と男性不妊症の関連が報告(2)されています。まずはこれら生活習慣病にかからないように、日常生活を見直すことが大切です。

日々の食事は精子の質や妊娠しやすさに影響します。偏った食事は栄養不足を招くため、1日3食、バランスの良い食事を心がけましょう(*3)。
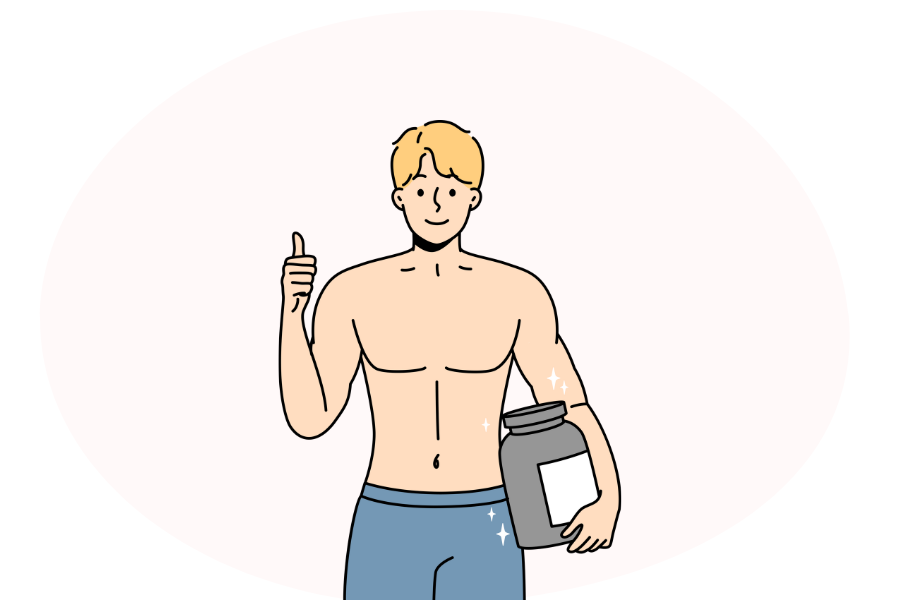
以下の生活習慣も精子の状態に影響を与えます。

精子は熱に弱いため、サウナや長風呂、ひざ上でのPC作業などで精巣を温めすぎないよう注意しましょう(*3)。

男性不妊は、珍しいものではなく不妊カップルの半数に関わる身近な問題です。原因は多岐にわたりますが、精液検査などの基本的な検査で現状を把握し、適切な治療や生活改善を行うことで改善が期待できます。
「妊活=女性の問題」ではなく、男性も積極的に検査・治療を受けることが妊娠への近道です。
参考文献
*1…一般社団法人 日本生殖医学会 生殖医療Q&A > Q7.不妊症の検査はどこで、どんなことをするのですか?
*2…日本泌尿器科学会 男性不妊症診療ガイドライン(2024)